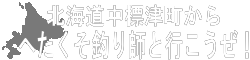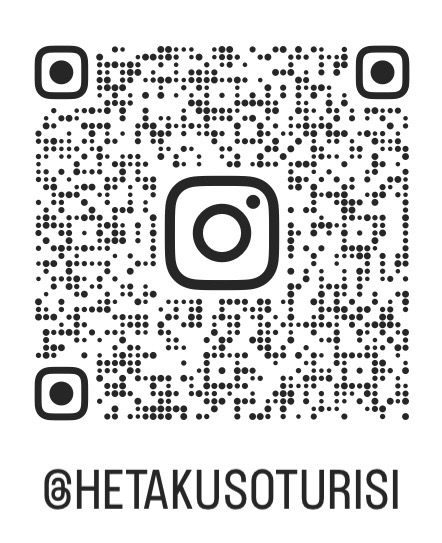2021年10月
今回はヒメマスのポイント調査です。
屈斜路湖に秋の訪れを感じるころ、湖岸は俄かにざわつきはじめます。それは産卵を直前にひかえた色鮮やかなヒメマス達と、それをターゲットにしている釣り人達が集まるからです。
※産卵魚の釣りを推奨しているわけではありません。
春のヒメマスは銀ピカに輝き、食べてみてもとてもおいしい魚だと聞いたことがあります。
秋のヒメマス釣りは岸寄りしているもののかなり難しいようで、思うような釣果を上げられず志半ばで去っていく釣り人も少なくありません。
しかし、腕に自信のある釣り人はしっかりと釣果を上げて、ほんの一時のチャンスを物にしています。
10月初旬、夏も終わり色鮮やかな秋の道東。今回も砂湯にて無事にキャンプを楽しむ事が出来ました。私は今までヒメマスをターゲットとして釣りを行ったことがありませんが、帰り道は少し遠回りをして、ヒメマスのポイント調査に乗り出しました。
色々と調べてみると今まで知らなかった事が多々出てきましたので、少しまとめてみようと思います。

RECAMP 砂湯(砂湯野営場)にて
目 次
秋のヒメマス水中動画
産卵の為に岸寄りしたヒメマスの動画です。
産卵床を守ろうとする雄特有の行動も見られ興味深い映像ですので、ぜひご覧ください。
ヒメマスとは
ヒメマス(姫鱒、Oncorhynchus nerka)は、サケ目サケ科の淡水魚の一種で、湖沼残留型(陸封型)のものを指す(降海型のものはベニザケという)。1904年(明治37年)、北海道庁水産課の職員により命名された。アイヌ語での名称は、「薄い魚」を意味するカパチェㇷ゚ (kapacep)。北海道では本種をチップとも呼ぶが、語源はアイヌ語で「魚」を意味するチェㇷ゚ (cep) が訛ったものである。
Wikipediaウィキペディア


屈斜路湖(くっしゃろこ)とは
北海道東部(道東)の弟子屈町にある自然湖。
日本最大のカルデラ湖。
全面結氷する淡水湖としても日本最大の面積。真冬の御神渡り現象が有名。

屈斜路湖が出来るまで
今から約30万年前に噴火をして大きな大穴が出来たところに雨の水や湧き水が溜まって湖が形成され、今から約3万年前に湖の原型とも言われてる屈斜路湖が誕生しました。
その後、湖底噴火を繰り返し今ある川湯温泉地区や屈斜路地区を形成し湖の真ん中にポツンとある中島や和琴半島もその時の湖底噴火で突出した島です。

屈斜路湖での動力船の利用
水上バイクやモーターボートなどのウォータースポーツでも有名な屈斜路湖でしたが、動力船の利用により騒音をまき散らしたり、事故やトラブルの発生が後を絶たず、令和3年より個人の利用による動力船の利用が禁止されました。
自然公園法第20条第3項第17号の規定に基づき、阿寒摩周国立公園の特別地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する区域及び期間を次のとおり指定する。
区域 北海道川上郡弟子屈町(屈斜路湖水面の全部)
期間 4月1日から12月31日まで (※令和3年は10月1日から12月31日まで)
屈斜路湖における放流の歴史
 秋の屈斜路湖林道
秋の屈斜路湖林道
屈斜路湖地震(昭和13年)
1938年(昭和13年)の湖底噴火で酸性化し、魚類がほぼ全滅。1954年(昭和29年)に漁協が解散し、漁業権も消滅した。
放流の歴史
酸性度の低下に合わせて、1968年(昭和43年)から町がウグイやニジマス、ヤマメなどを放流してきたところ、自然繁殖で魚影が回復するようになった。ヒメマスは1994年(平成6年)度以降に町と水産庁が放流し、個体数が一気に増えた。
参考資料↓
弟子屈町による放流と採捕実績(平成29年度末現在) (PDFファイル: 330.4KB)
今現在の屈斜路湖、特にそこに棲みつく魚類に関して言えば自然のあるがままのスタイルではないと言えるのかもしれません。人の手を加え、守り育てた結果が今に繋がっていると言えるでしょう。
ちなみにヒメマスは屈斜路湖の在来種ではありません。


産卵岸寄りのヒメマス釣りについて

屈斜路湖における秋のヒメマス釣りは産卵期に岸寄りした個体を狙って行うものですが、特に明確な禁止行為とはなっていないのが現状です。
一応下記(フィッシングルール)に記す通り『産卵魚を守るため、釣りをしないこと。』となってはおりますが、『流入河川では』と区分されています。ここをどう解釈するのかは釣り人に委ねられていますね。
- 屈斜路湖へ流入する河川では、産卵魚を守るため、釣りをしないこと。
- 稚魚を釣らないこと。
- キャッチ&リリースに努めること。
- 使用する釣竿は、1本とすること(予備竿を除く)。
- 資源保護のため、動力船によるトローリングやサビキ釣りをしないこと。
- 観光客が訪れる場所では、周りに十分注意すること。
- 民有地に駐車するときなどは、必ず了解を取ること。
- カヌーやヨットなど他の湖面利用者との調和を図ること。
- 危険防止のため、氷上釣りは、しないこと。
- 弟子屈町の遊漁巡視員のアドバイスに従い、安全で楽しい釣りに心がけること。
弟子屈町ホームページ屈斜路湖での遊漁より転載
上記はあくまで自主的なものであり、法的な強制力はありません。
スポーツフィッシングのメッカとも言われる道東の屈斜路湖。北海道の雄大な景色の中でダイナミックな釣りを楽しめることで有名なのですが、私自身この秋のヒメマス釣には以前より少々疑問を感じていました。
沢山の釣り人でにぎわっているので、観光資源として釣らせてもらえているものと理解していましたが、フィッシングルールを読む限り、どうやらそうでもなさそうだぞと言う思いに行き着きまして、今回弟子屈町の環境生活課へ秋の岸寄りヒメマスの釣りについて直接お伺いしてみました。
以下その内容。
その中で、魚類資源を守るために産卵魚を釣らないことをお願いしています。
また、将来にわたる魚類の維持保全のため、”キャッチ&リリース”も推奨しています。
すでにご指摘いただきましたが、産卵魚を守ることは魚類資源を守ることに繋がります。
今後も稚魚を育てるために引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
つまり流入河川に限らず、秋に産卵の為に岸寄りしたヒメマスを産卵魚とするならば、釣らない事をお願いしたい。
と言う事だと思います。
流入河川付近には魚が産卵場所として選ぶこともありますので、あえて避けている釣り人もいるそうです。
参考資料↓
屈斜路湖のフィッシングルール&マナー (PDFファイル: 930.6KB)
しかし、明確に表記されていない事にも少々疑問が残りますね。
実際に秋のヒメマスを狙いに来ている釣り人の中には、遠方より何日も滞在して釣りを楽しんでいる方もいらっしゃいます。
もちろんヒメマスだけではありませんが。
観光資源としての経済効果もあるのでしょう、そのような方々も地域としては大切にしなければなりません。
そのような理由で明確に表記しない、できない、と言う事もあるのでしょうかね。

調査を終えて
秋の屈斜路湖の湖岸には当然産卵の為にヒメマスが岸寄りしています。しかし、岸寄りしている魚種はヒメマスに限らず、ウグイ、アメマス、ニジマス等も多く含まれます。
昔、屈斜路湖にて超大型のニジマスを釣り上げた写真を見せてもらった事があり、デジカメの無い時代なので、初めて見る70オーバーの魚体に酷く驚いた事を今でも忘れていません。
その大型のニジマスは世代交代を繰り返し、今もどこかに潜んでいる事でしょう。そんな大物を釣り上げてみたいと思うのは釣り人であればごくごく当然のことだと思います。
季節に限らずターゲットとする魚種を選別する事は難しいでしょうが、産卵魚を守ると言う行為はすべての釣り場でのスタンダードであるべきだと思います。
私自身は馴染みの薄い屈斜路湖ですが、結氷期以外にはいつでも釣りを楽しむ事が出来、誰でも大物に出会えるチャンスは存在します。
そんな屈斜路湖が自然の成り行きだけで今の状態に維持できているのではない、と言う事を今回あらためて知る事が出来ました。
動力船の利用が禁止されたように、生息数の変化によっては、いつ釣りそのものが禁止されてしまうかわかりません。
いつまでも釣りが楽しめるように、あらためてフィッシングルールに沿った釣行を心がけたいものです。

今回使用したカメラはこちら↓
ソニー / コンパクトデジタルカメラ / Cyber-shot /DSC-RX100M3
ソニー アンダーウォーターハウジング MPK-URX100A
ランキングにご協力ください。m(_ _)m↓
ツイッターもやってます!
北の釣友byへたくそ釣り師
Follow @northfishers
YouTube動画もあります!
チャンネル登録お願いします↓
登録1000人↑チャレンジ中!