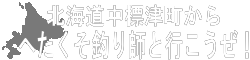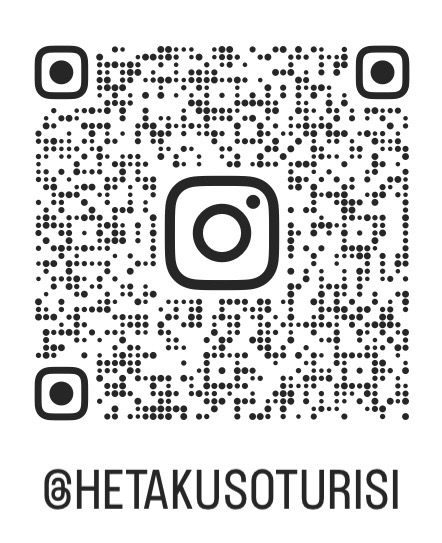11月中旬 地元湿原河川にて

秋、と言うには紅葉も既に散り落ち。冬、と言うには雪の便りがいまだ届かず。晩秋から初冬へと移り変わるこの時期は身体がまだ慣れていないせいか寒風がやたらと身に染みる。そんな肌を突き刺すような冷たい空気が漂う地元湿原系河川に、このあと目を疑うような巨大なアメマスを目撃することになる。
はたして、その巨大魚を釣り上げる事が出来たのか?
これまで散々釣りの対象としてきたアメマス。改めてその生態について今まで書き記したことが無かったので、まずはここで少しおさらいしてみたいと思う。少しと言うか結果としてかなり長くなってしまった。
とんでもなく前置きが長いので、興味の無い方は飛ばして読むことをおすすめしたい。

目 次
アメマスとは
- 学名 Salvelinus leucomaenis leucomaenis:サルベリヌス・ロイコメニス・ロイコメニス
- 英名 White spotted char:ホワイト・スポッテッド・チャー
- 科名 サケ科サケ亜科イワナ属
- 分布 北海道 本州(利根川以北)
- 食性 小型魚類や甲殻類、昆虫などを食べる動物食性
アメマスとエゾイワナの違い
上記のように、河川に残る個体がエゾイワナとされているが、見た目の明確な区別はない。このため、一般的には総称としてアメマスと呼ばれる事が多い。
過去の画像から、その個体差について少し見てみよう。




いずれも30cmに満たない個体ではあるが、釣れた時期については皆バラバラ。おそらくいずれかはアメマスで、いずれかはエゾイワナなのであろう。見た目の区別はつけ難い。アメマスとエゾイワナは同種であることの所以。
海アメマス・遡上アメマスについて
私が釣りの対象としているのは、陸から狙う岸寄りの海アメマスか夏以降に遡上開始する大型の遡上アメマスの2つのパターンに分類される。




これらについてはすべて海からの遡上個体だと考えられる。色濃い陸封のエゾイワナに比べると、やや銀毛にも似た美しい魚体となっている。一枚目の画像については太平洋サーフでの釣果。やはり降海するタイプのほうが平均的に大型化する傾向がある。
アメマスの遊漁規制について
阿寒湖や塘路湖などの漁業権設定区域または一部私有地を除いて、アメマスについてはイワナの一種という扱いになり、殆ど規制の対象とはならない。
いわゆる一般的な「サケ・ます釣りに関する規制」にはアメマスは該当しない。規制の該当魚種としては(さくらます・からふとます・べにます・ぎんます・ますのすけ)であり、アメマスはイワナの仲間との認識である。
よって、サケマスの河口規制が設定されている場所についても厳密にはアメマス釣りは可能との事だが、密猟者と勘違いされてしまうため、やらないほうが無難と言えるだろう。
北海道水産林務部水産局漁礁管理課サケマス・遊漁内水面グループ(TEL011-204-5485)にて確認済み。
川アメマス釣りのポイントとなる河川について
北海道の殆どの河川と沿岸部がアメマスの生息域となるが、どういうわけか知床半島の河川と沿岸部には昔から根付いた様子はない。
私の釣行結果から言うと、やはり湿原系の河川には多くのアメマスが生息している。いわゆる山岳系といわれるゴロゴロとした石や岩が混在する急流河川には、ごく少数のみしか確認が出来ていない。
私的な感覚で申し訳ないが、広い汽水域(海水と淡水が混ざる区域)が存在する河川には特に多くのアメマスが生息しているという感覚がある。ここ中標津町からの近場河川では当幌川、春別川、風連川等が上げられる。
他に北海道の道東で有名所と言えば釧路川、音別川、十勝川、茶路川などが上げられる。
アメマスの釣り方・タックルについて
この記事を読んでくれている方にとっては、ここが一番気になるところではなかろうか。しかしこれはあくまでも私個人の経験と見解での記述なので、見当違いな内容であるかもしれない事をご理解をいただきたいと先に記しておくことにする。
先にも記したように、アメマスにとって捕食の対象が小魚や昆虫となる為、それに模したルアーやフライを使う事になる。当たり前の事だが、その疑似餌の演出効果で釣果は大きく左右される。
基本的には他の川魚と釣り方はなんら変わらないと私自身は思っているのだが、経験のない人からすると何をどうして良いのか見当もつかないらしい。
小・中規模河川編
とりあえず、まずはこの動画を見てほしい。↓16分50秒
この動画の撮影時期は12月の真冬の季節。厳冬期のニジマスやアメマスの釣りについてヒントとなる事が随所にあるように思う。
この時の捕食対象はご覧の通り魚卵だ。この環境下ではスプーンやミノーでのルアー釣りでは少々難しいかと思う。ではフライフィッシングでエッグフライを利用すれば釣れるか?
答えはイエスでもありノーでもある。
どういうことかと言うと、あくまでも魚から見てエッグでなくてはならないと言う事。
聞けば当たり前に思うかもしれないが、これはこれで意外と難しい。
動画の映像だけでは分かりづらいがこのポイントは狭く流れが速い、しかも水深が深く水上からは偏光グラスでも魚影の確認は全くできない。魚と言うものはつくづく隠れるのが上手いものだと感心してしまう。
では、答えは何であろうか。
生餌のイクラを使った脈釣りではないだろうか?おそらくはそうであろうと思う。
が、今は疑似餌にこだわった釣りをしているところなので疑似餌にこだわった解釈をしてみたいと思う。
エッグフライを使用しての脈釣り、いわゆるアウトリガースタイルにてフライを流してみれば、一発ヒット!
とはならなかった。
色や重さ、いかに本物に近く、そして狙いのごくわずかなエリアに流し込まなくてはならない。ごくごく自然に、と言うのが今回の正解だと思われる。結果としては腕が未熟な為にヒットとはならなかった。
では、ルアーではどうだろうか?
この時使用し、実績があったルアーはこちら↓
 ブラックライト無
ブラックライト無 ブラックライト有
ブラックライト有この画像はブラックライトを当て、紫外線の反射を撮影したものである。これ以外のルアーには全く反応が無く、運良くアタックしてきたのがこのルアーである。
この時の釣果がこちら↓

そう、アメマスではなくニジマスがヒットしてきた。この時このポイントでは残念ながらアメマスをヒットに持ち込むことが出来ず、この一本のみの結果となる。たまたまアメマスより先にニジマスがヒットしてしまった、と思いたい。
海水、淡水にかかわらず一部のサケマス群には、このUV効果が識別できる種も存在すると言う。もし、万が一このUV効果に反応したのだとした場合、この釣果に至った背景を説明出来やしないだろうか?
魚卵単体にUV効果があるかどうかは確認できていないが、ルアーのUV効果に反応し、何かしらの捕食モードに入ったのだとしたらどうだろう。あくまでも仮説でしかないのだが、とても興味深い結果となった。
捕食対象となる物が魚卵だった、と言うだけでこのぐらいの予想や推測、思惑までも含めて考えなくてはならない。決して難しく考える必要はないのだが、釣りが空想の遊びであると言う事がおわかりいただけるだろうか?
釣りにはマッチザベイトという言葉がある。実際の餌に合わせていこうと言う考え方だ。
春から夏にかけてのサケ稚魚捕食シーズン。
夏から秋にかけての昆虫シーズン。
秋から冬にかけての魚卵シーズン。
冬から春にかけての何かわからないシーズン。
それぞれのマッチザベイトを考え選択する必要性があるが、ここで大事なのは形だけを模すのではなく、魚から見て実際の餌に似せていかなければ釣果に結び付かないと言う事だ。いかにフライやルアーを駆使して実際の餌に見せかける。ここ大事、魚目線で見せかける事が大事だと言う事。人の目ではなく、魚の目で、での事。
マッチザベイトの考えには異を唱える人がいるが、あくまでも確率が高い引き出しの一つと捉えるのが妥当だと思う。そこに執着すると釣れるものも釣れなくなる。0%を限りなく100%に近づけようという、あくまでも釣果に結び付ける一つの手段でしかない事を忘れてはいけない。
スプーンひとつで稚魚にも、昆虫にも似せていく事が可能であると私は考えている。もちろんミノーに関しても同じことがいえるだろう。
さて、
では具体的な釣り方はと言うと。

ルアーフィッシングの場合
ルアーの場合は基本的にただ巻きで良い。
なんだ、それだけかと思うかもしれないが、本当にそこが重要になってくる。アメマスはイワナの一種なので基本的に獰猛だ。したがってアメマスにしっかりルアーを見せる事によって食い気のある個体はそれだけで釣れてしまう。釣りの中では難易度的にはけっこう簡単な部類に入る。
個体数が多いので中型クラスまでは十分にそれで対応できるだろう。しかし問題なのはそれでは反応しない中型から大型のクラスをいかに攻略するのか、と言う事。これに関してはこの後記述する釣行記をご覧いただきたい。何かしらの答えは導き出せるだろうと思う。
私の使用するルアーはスプーンとミノーがメインで5g~28g、5cm~の重さ、大きさの物が殆ど。それぞれ何種類かのカラーバリエーションも用意している。アメマスに関してはチャートリュースカラーと赤金系が多い。
ロッドについては7フィート~8フィートもあれば十分。あまり長いと藪の中で取り回しに苦労する。
ラインは色々と気を付けなければならない。基本的には16lb以上は用意したい。ナイロンやフロロ等それぞれの特性や好みもあると思うので、慣れ親しんだラインで良いと思う。不意の大物に根にまかれラインブレイクとならないようにするために、気持ち強度を増したほうが尚よい。私は2.5号、30lb前後のPEラインに20lbのフロロカーボンのショックリーダーをFGノットで結線し使用している。
厳冬期の常時マイナス気温になる季節には16lb~20lbのナイロンラインを使用している。ロッドのガイドが凍り付く為にフロロやPEは凍結し固着してしまうのを防ぐためだ。
- ルアー スプーン5g~20g シンキングミノー45mm~90mm
- ロッド 7フィート前後
- リール スピニング2000番前後 ベイトリール各種
- ライン ナイロン12lb~ PE1.5号~
- リーダー 16lb~
フライフィッシングの場合
フライフィッシングの場合はやや難易度が上がる。
ルアーフィッシングよりかはクリアしなければならないハードルがいくつかある為だ。湿原河川になれば尚更で、キャストするためのスペースが十分に取れない場合が多く存在する。どうしてもフライフィッシングでなければならない場合を除いては無理せずルアーフィッシングを選択したほうが無難と言えよう。
- フライ ウーリーバガー ニンフ ウェット スカッド
- ロッド #4 #5 #6 シングルハンド
- リール 各種
- ライン DT・WF4・5・6F
- リーダー 2X~
- ティペット 12lb以上
海アメマス・サーフ編

サーフで狙う海アメマスについては、ヒットパターンこそハマれば実に面白いように良く釣れる。しかし、潮回りや朝夕のタイミングを外すとこれまた全くと言って良いくらいに釣れなくなる。
サーフに出現するアメマスは基本的にベイトフィッシュを追い回すことで岸寄りしているので、釣るのは容易い。ベイトフィッシュが水面直下を泳いでいるマズメ時がねらい目となる。
ポイントの選定は結構難易度が高い。広く変化の乏しいサーフなので、アメマスのライズやボイルを見つける事が釣果に結び付きやすい。ライズやボイルが無い場合は、広くランガンしながら当たりを探る。
離岸流を運よく見つけ出す事が出来たらそれはチャンス到来だ。うまくジグを離岸流に乗せる事が出来ると、リーリングをしなくともいつまでもジグが泳いでくれているのがラインとロッドを介して手に伝わってくる。この時、待ち構えているアメマスがいれば即ヒットとなる。逆に言えばこれでヒットしなければ魚影はかなり薄いものだともいえる。離岸流には特に注意を払いたい。
私の海アメマスの釣り方は本当に単純で、ジグの遠投早巻き。
それだけ。
本当にそれだけで面白いように良く釣れる。その代わり100mライン全部出し切るくらいに遠投し、ハンドルが取れるのではないか、と言うくらいに早く巻く。

- ルアー ジグ、ジグミノー他 遠投可能な物
- ロッド スピニング 10フィート~12フィート
- リール 2500番~3000番
- ライン PE1.5号
- リーダー 16lb フロロカーボン
アメマスの食べ方 味・料理
一般的にアメマスを食す習慣はあまりないように思う。地元の市場に極まれにセリにかけられることもあるとの事だが、食堂などのメニューにアメマス料理を目にすることはまったくない。
私も一度だけ海で釣り上げた砲弾型のアメマスを食してみようと持ち帰ったことがあるが、胃の内容物と背の脂身が殆どで、肝心の身は水っぽく焼いても煮てもあまりおいしくなかったという印象が強い。
しかし、その道のプロと呼ばれる方は何処にでも存在していてクックパッドにも多数のレシピが掲載されている。どのレシピを見ても実に美味しそうに調理されているだけではなく、実際に美味しいとの事だ。
なかでもフライとムニエルが特に人気らしい。
フライに関しては身が他のサケ類に比べると柔らかいのでふわっとした感じに仕上がるとの事。
ムニエルに関してはしっかりと味付けすることにより水っぽい身が気にならなくなるとの事らしい。
食に関しては私の実体験ではないので憶測になってしまうが、ここまでアメマスの料理が広く認知されているとなると、試してみたくなる。
アメマス大量駆除の噂
漁業資源としてあまり価値が無いとされて来た為か、近年アメマスは『サケの稚魚を捕食する害魚とされ一斉駆除されていた』らしい。との噂が絶えない。
私は自分で目撃したわけではないが、2000年1月に発行された”NorthAngler's Vol.7 新春号”によると1990年頃までは実際に行われてきた旨の記載がある。今はどうなっているかわからないが、どうやらそれらは事実と言わざるを得ないだろう。
この問題に関してはたいへんデリケートな問題で、単に釣り人目線や自然・動物保護の観点だけでは解決しない現状がありそうだ。北海道の水産資源でもある秋サケ。このサケの漁獲量が激減しているのである。
そこで行われてきたのがアメマスの大量駆除と言うわけだ。つまりサケに育つ前の稚魚をアメマスに捕食されてしまわないように、サケ稚魚保護の観点からアメマスを捕らえてしまおうと言うことだ。もしかしたらサケに限らず他の水産資源の保護の目的もあるのかもしれない。例えばエビ等。
アメマスを捕えてしまえば、サケの漁獲量が増えるのかどうかはさておき、物理的にはサケ稚魚の生存率は少なからず上昇するだろう。しかし、サケ稚魚の生存率は上昇してもサケの成魚が生まれ故郷の川に帰って来る率が上昇するかは甚だ疑問に思う。分母が多ければそれに比例して分子も増えるだろうという考えに基づくものだと思うが、自然環境はそれほど単純ではないだろう。
サケ自身が成魚になるまでの餌となる栄養素、そして育成に必要な自然環境のキャパシティが十分に余裕があるのかどうかも考えなくてはならないのではないだろうか。
私はこのふ化事業そのものが長年行われて来たであろうことから、毎年放流された稚魚が自然環境全体からすると生態系のバランスを逆に崩してしまわないのだろうかと言う心配もある。
近年はふ化事業と自然産卵を促す両軸での取り組みが注目されているようだが、世界的な海洋環境の悪化から効果が期待できるかどうかは判断が難しい所だ。これだけ科学が発達した世でも未だ解明できないところは致し方ない。いずれにしてもサケマスだけではなく地元産業が活気に沸いてくれることを切に願う。
初冬の湿原河川アメマス釣行記

さぁ、ここからが今回の釣行記。いつものごとく前置きが超長くなってしまった。
実際の釣果なくして釣りの何たるかは語れないものと考えているので、結果としてはかなりの大物を釣り上げる事が出来ており、御覧いただいている皆様にとって何かの役に立てていただけたらと思う。
アメマスの近況

毎年幾度となく挑戦し続け、返り討ちに合う秋の湿原河川。対象となる魚種はもちろんイトウとアメマス。しかし、ここ数年、秋のイトウ・アメマスに関してはこれといった釣果には恵まれていない。
イトウはそもそも個体数が少ないので滅多にお目にかかれるものではない。アメマスについては年々、小型減少傾向にあるために大型個体を目にする機会はすっかり減ってしまった。そのためかさっぱりモチベーションが上がらないのが今の現状。
それでもここで挑戦をやめるわけにはいかない。と自分自身に言い聞かせ、まったくもって身勝手で根拠のない自信を無理やり奮い立たせ、またも湿原河川へとやってくる。
昼間でも身震いするような寒さだが、地球規模から見たときには温暖化が進んでいるようだ。昨日もフィリピン沖で台風が発生したとのニュースがあった。詳しいメカニズムについてはわからないが、どうやら台風は海水温、特に表面温度の上昇で発生してしまうらしい。11月に入ってもなお発生していると言う事は海と川を行き来するサケやマスたちにとって影響がない、とは言えないだろう。
サクラの花が平均気温との相関関係によって開花するように、魚についても水温との相関関係が無いとは言い切れない。現に自然に生きる者たちは1年の変化を何で計っているのだろうか?草花は気温?魚は水温?日照時間や太陽光の傾きなんかも関係しているかもしれない。魚に関してはそれぞれに適水温もあるでだろうから、特に水温については敏感であると思う。
であるならば、
海だけではなく、川の平均水温についても調べてみると面白いかもしれない。
水温の変化によって遡上時期や産卵時期に変化が出てきている可能性もある。
初冬の湿原河川に巨大アメマスを目撃する

今まではそうであったから、これからもそうである。と言う事は絶対にない。現に気象変動により大規模災害が多発している現状である。アメマスの産卵時期や越冬場所等も大きく変化している可能性がある。
アメマスをターゲットとする時、ほとんどの場合は中流から下流域に目星をつけて入渓するのだが、今回は上流域から調査もかねて見てみる事にした。
よって、入渓ポイントとしては、人が入っていなさそうな上流域に狙いを定めて調査的な感覚で入渓する。
所用を済ませてからの11時スタート。久しぶりの湿原河川に少々胸が躍っているのが自分でもわかる。
時期的には11月中旬なので、アメマスの行動パターンからすると産卵を済ませた個体が越冬場所を探し川を下っているという予想が立てられる。したがって、この上流域に残っているのはごくわずかのエゾイワナか産卵まもない個体だと思われる。難易度的にはそれほど難しくはないだろう。
ミノーのただ巻きで案の定、開始まもなく産卵後だと思われるアメマスがヒットした。

白い斑点がオレンジ色に染まっている。雄特有の婚姻色だ。大きさは40を少し超えたくらいだと思うが、サイズのわりに良く引くパワフルなやつ。
ここ数年はこのサイズがやたらと多いように思う。これはこれで北海道のれっきとしたネイティブトラウトなので、近場で気軽に狙える釣りのターゲットとしては申し分ない。
しかし、やはり大物を釣りたいと思うのが釣り人というもの。釣れるサイズほとんどがこのサイズでは贅沢な事はわかっているが、飽きてしまうのである。モチベーションがなかなか上がらない要素の一つでもあると言えよう。
二時間ほど釣りくだり、そろそろ折り返さなくてはならない時間帯。アメマスが居つきそうな大場所を探し当てた。
11月の午後ともなると相当に陽が傾き、陰になるポイントは偏光サングラスをかけても水中はとても見にくい。
しかし、間違いなく居ついているであろうそのポイントを足音を立てず静かに目を凝らしてそうっと覗き込んでみた。
木々の間から沈みかけた太陽の光が、ちょうどその深い瀬を照らし出している。その水底におとな一人分くらいありそうなバイカモが大きく揺らめいているのがわかる。脇にある奥側の流木付近が気になったが、バイカモの前後を細心の注意をはらって探してみる。しかし、それらしい魚影は確認できなかった。
おかしいな、ここでいないわけがないと再び目をやったその先に、先程奥側にあった流木がバイカモのこちら側へ移動している。
いや、それは流木ではなく正しく巨大なアメマスの魚影だった。
お気楽釣行モードから一変して本気釣行モードとなる。
おそらく自己記録(77cm)を超える事が出来るとするならば、これはまたとない機会かもしれない。
手持ちの引き出しが少ないお気楽モード、得てしてその様な時ほど不意を突かれるものである。
一度だけ反応を見せたヤマメカラーのミノー。
いきなり突進してきた大きな口には残念ながら飲み込まれる事は無かった。
そして魚影は静かに姿を消す。
巨大アメマスに再挑戦するも
その日の夜は中々寝つきが悪かった。
確かに巨大なアメマスを目撃し、一度とはいえミノーで反応を見せたのは事実なのだが時間が経つにつれ、あれは錯覚だったのではないかと自分で自分を疑う始末。
いや違う。あれは間違いなく現実に起こったことで決して目の錯覚ではない。と何度も頭で繰り返し思い出す。
なんとも、後味が悪い釣りになってしまった。
気を取り直して次の休日。
前回と同じポイントに訪れてみたが、やはりと言うか当然あの巨大アメマスの姿はない。
どこかにいるかもしれないと、しばらく釣り下ってはみたが発見するには至らなかった。
さて、どうしたものか。
このまま諦めるわけにもいかず。
河川の完全結氷まではまだ数日あると思われるので、アメマスの行動パターンから推測し、今回の大型個体を同じ水系の河川に絞りこんで追い求めてみようと思う。
中流ポイントへ移動
中流域に限らず湿原系の河川には上流から下流まで至る所に地下から水が湧いているところがある。

この画像は地上の水が湧き出ている箇所。
すでに凍結し始めているが、まだちょろちょろと水が染み出ている。
地下水脈で水が湧き出ているところは、比較的水温が安定している傾向があるのでアメマスの越冬場所には適切なのではないかと、私は推測している。
そんな湧水が出ているであろうポイントに、私は毎年のように訪れている場所がある。ここで出なければ打つ手がない、と言うようなところだ。
間違いなく越冬アメマスはそこに付いていると私は確証している。

やはり出た。少しサイズアップの50弱。
うん、少しずつ近づいているような気がする。しっかりとミノーを追い、食い付いている。予想通りの展開。
さすがにここまでくると越冬アメマスの群れの数が凄まじい。何十、いや百数十と言っても過言ではないくらいの群れが存在する。しかもサイズは40弱くらい。どれもこれも同じサイズで行動している。
私の性格上、この集団行動にも興味がそそられる。これは一体どういうことだ?と。しかし、とりあえず今回はそっとしておくことにする。狙っているのはあくまで大型のモンスタークラスだ。
今回も大型には出会えずにいた。
そうなると狙いは最下流域の越冬ポイント。結氷までの時間との勝負でもある。
アメマス越冬ポイント最下流域

さすがにこの川幅までなるとポイントの選定に苦労する。
過去の実績をもとに区画を定めてじっくりと攻め切る事にする。
基本的に大事なことは、この時期のアメマスはベタ底に定位していると言う事と、ある程度餌になる物が流れてくる箇所、又はその近くに定位しているであろう事が考えられる。
ただ広く闇雲にキャストを繰り返すだけでは、時間ばかりが経過しヒットに持ち込む効率が非常に悪い。このようなポイントでは、水深や流速の変化をいち早く見極めたい。
そして、早巻きやただ巻きだけではアメマスの口を使わせる事は出来ない。しっかりとルアーを沈ませ自然の餌に似せたように水の流れに乗せる。これは、阿寒川のニジマスに見る傾向と類似した捕食行動。積極的なガンガンの追い食いではなく、負圧を利用した吸いの捕食行動。より自然なベイトを捕食する行動とも言える。
追わせるのではなく、こちらから合わせるようにルアー単体をコントロールする事。そうすることでヒットする事が多いのが過去の実績からくる私なりの答えである。
食わせのパターン化。追いで食わせるのか待ちで食わせるのか。主導権はいつもこちらにあると言う事を忘れてはいけない。
アメマス釣行おすすめルアーで再び挑戦!
それにしてもルアーを食わせるのには本当に苦労する。




あの手この手で何とか食わせに成功した個体。
海が近いせいか鱗が銀色に光っていて、とても美しい魚体となっている。これは産卵に参加しないタイプなのか。

アメマスを釣り上げた経験がある方はご存知だと思うが、アメマスは陸に上げると、このように立つ。しかもその後にょろにょろと川に戻ろうとする動きを見せる。
この行動は他のサケマスにはなく、イワナ系の魚に多く見られる。進化の過程でそうなったのだと思われるが、緩い大きな流れの深い底に、じっと動かずに獲物を待ち構えている様を想像すると、アメマスがフィッシュイーターと呼ばれるに相応しい獰猛な魚だということがわかる。
その獰猛なフィッシュイータが待ち構えているだろう、というポイントをやっとの思いで見つけることに成功する。
流れてくる餌を待ち構えているには絶好の場所。大きな流れの集まる中心にわずかな障害物を確認できた。
すぐに投げ込みたい衝動を抑え、ここは慎重に対処してみようと思う。
過去の経験から導き出す答えはいつも、流れに合わせて川底をころころと転がすように流すことだ。
結果的に魚へのアピール力は一番強い流し方だと私は思っている。
よく、ルアーを流すときに点で追わすか線で追わすかの議論があると思うが、人から見ての点と線、魚から見ての点と線での見かた見え方で、全く逆の考え方になってしまう。
人から見て点に集中しているように見えて、実は魚には線でのアピールになっているという事実。
魚から見ての点と線の問題については、また別の機会に詳しく記述したいと思う。
上流域に比べると水の透明度はやや劣る。十分に沈みアピール力のあるカラーを選択したい。
私が選んだルアーはこれだ。
アメマス釣りには定番中の定番。私がおすすめするアメマス釣りには欠かせないルアーの一つだと言えよう。闇雲に選択したわけではないと言う事だけ付け加えておく。
このルアーを使用し障害物を狙うときには特に注意が必要だ。自重があるので、底まで一気に沈み込み油断するとすぐに根掛かってしまう。
今回もそうだ。
慎重に狙いを定めてキャストし、十分に沈めて底についた瞬間、ルアーが止まる。
ラインとロッドを介して伝わってくる川底の針掛かりした物体には、全く生命感が感じられなかった。
しばらくたっても微動だにしないそれは、まさしく根掛かり以外の何物でもないと私は思った。
しかしである。
根掛かりを外そうとビュンビュンロッドを振り続け、水に突き刺さるように見えたラインが先程よりも上流側へ移動しているようにも見える。
一瞬で血の気が引くのが自分でもわかった。
いや、これは魚だ。しかもでかい。
根掛かりだろうと思ったら魚だった。釣りによく聞くあるある。の、それだ。
ようやく違和感に気付き走り出したそれは、私の眠っていた釣り人としての勝負魂を引き起こさせるには十分だった。
さいわい根掛かりだろうと思ってしゃくり上げたロッドが、うまく追い合わせの効果を発揮してくれたらしい。しっかりとフックアップできたようである。
引きに関しても、物凄いパワーとトルクがある。爆発的な激しさは無いが、重く力強い引きは、まるで飛び出した大型犬のリードを無理やり持たされた感覚のようである。
ある程度の大型を予想してのタックルなので、そのような重く強い引きに対しても十分に対応できる。備えあればなんとやら、と言う事だ。
寄せては走り、寄せては走る。
そのやり取りを幾度とこなし、片手で準備した折り畳みネットにてようやくネットインする事が出来た。
既に冷え切っていた身体が、すっかり汗ばんでいることに気が付いたのは、やっと陸に上げた魚体にスケールを合わせようかと言う時だ。
どうだ!これぞまさしく北海道のネイティブトラウト!モンスターアメマス!

76cmのそのビッグな魚体はまさしくアメマスの中では最大クラスだと言えるだろう。しかも見事なプロポーション。このような魚とファイト出来る事を北海道の大地に本当に心の底から感謝したい。
【水中動画】湿原河川のアメマス群
アメマス釣りおすすめポイント
アメマスの釣り情報
釣りを終えて
この時期としては珍しい砲弾型。海から遡上したばかりかのように見えるが、まだサケの捕獲施設が設置されているのでその線は薄い。いったいこの個体はどこから来たのだろうか。産卵後というわけでもなさそうだ。
この流域でのアメマス世界は混沌としている。産卵を終え、上流より下ってきた個体。陸封の個体。海から流入してきた産卵には参加しない個体。これから産卵場所へと向かう個体。
越冬場所を求めて行動パターンの異なるアメマス個体群が入り混ざっている状況だ。
今回の釣行のターゲットとしては産卵後の越冬地に潜む大型の個体に的を絞り挑戦してみた。結果は御覧の通り素晴らしい釣果に恵まれる事が出来たが、またしても新たな疑問を生む事になりそうだ。
このサイズを遥に凌駕する個体が間違いなく存在している、と言う事だ。
何度も書き記し、何度も思う事だが最終的には望みの結果とはならないのが釣りの難しいところでもあり、面白いところでもある。
秋の河川に点在するアメマスの生態。なぜそこに居るのか、または居たのか?
捕食対象物は何か?
予測を立て実践してみても、なかなか思い通りにはなってくれない。
あとがき
今回の記事は、アメマスに関して私の実体験4回の釣行に渡り、出来うる限りの情報を一つの記事としてまとめてみることにチャレンジしてみた。
一部表現方法が難しく、専門用語を多用しているところはご容赦願いたいと思う。気になるところはぜひネットで検索していただけるとありがたい。すぐに答えが出てくると思われる。
これだけ多くの釣り人を魅了してやまないアメマスだが、それは謎が多い為なのかもしれないと改めて感じさせられた。同じ北海道でも道東と道南では、アメマスの行動パターンが異なるらしい。アメマスの分布についても道南や道外、ロシア方面についても興味がある。
これからもまだまだ私の釣り人生を楽しませてくれそうだ。
ランキングにご協力ください。m(_ _)m↓
ツイッターもやってます!
北の釣友byへたくそ釣り師
Follow @northfishers
YouTube動画もあります!
チャンネル登録お願いします↓
登録1000人↑チャレンジ中!