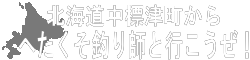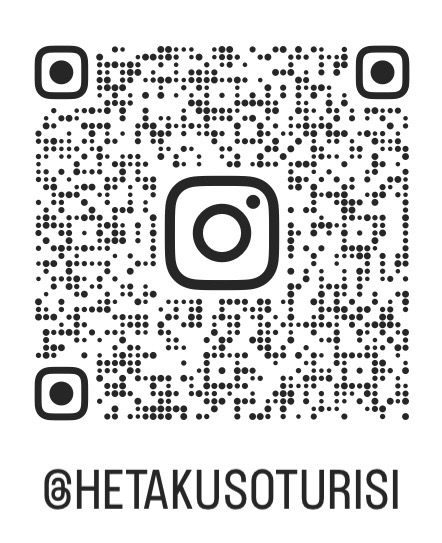皆さんはエゾモモンガと言う北海道に生息する野生の小動物をご存知でしょうか?
最近は、その愛くるしい姿や表情から世界的に注目を集めておりまして、初心者の方からプロのカメラマンまで数多くの方々の撮影対象になっているようです。
過去数カ月に渡り準備を進めてきて、ようやく撮影に成功いたしました。
今回も釣りのお話ではありません。
北海道のアクティビティ、大自然を満喫です。
興味のある方、お時間のある方はお付き合いください。
目 次
エゾモモンガの撮影結果【YouTube動画】
まずは下の動画を見てください。今回の成果です↓
一応4K動画ですので、できるだけ大きな画面で見ていただけると細部まで見る事が出来ると思います。
あらも目立ちますが・・・
エゾモモンガとは
蝦夷小鼯鼠は、ネズミ目齧歯目リス科リス亜科モモンガ族モモンガ属タイリクモモンガ種の亜種で、日本の北海道に生息する固有亜種である。
Wikipediaウィキペディアより引用
分布
本種は北海道全域の平野部 - 亜高山帯にかけて分布し、森林(常緑針葉樹林・落葉広葉樹林)に生息する。札幌市内の森林公園・円山動物園付近にも生息しているが、北海道島嶼部・千島列島には生息していない。
市街地の公園・学校の林・鉄道の線路沿いにある防風林・住宅地近くの雑木林などといった環境にも生息する。しかし夜行性で警戒心が強いことに加え、一生のほとんどを樹上で過ごすため継続して観察することは難しく、詳しい生態はあまり知られていない。
Wikipediaウィキペディアより引用
特徴・活動時間
本種は夜行性の小動物であることに加え、一度の滑空により高距離を移動するため発見・追跡が非常に困難である。加えて一生のほとんどを樹上で過ごし、天然の樹洞・キツツキ類の古巣を巣穴として利用するため捕獲も困難である。そのような特性に加え、人間にとってはほとんど利害をもたらさない動物であったためあまり注目されず、かつて本種の生態はほとんど研究が進んでいなかったが、小鳥用の巣箱を巣穴として利用することが判明したことで電波発信機を用いたテレメトリー法による追跡調査が可能となり、その生態が明らかになっていった。
活動開始時刻・終了時刻は日没・日の出時刻の季節変化に比例して変化する。春 - 秋(5月 - 10月)にかけては日没から平均15 - 20分程度で巣から出て活動を開始し、何度か巣に戻って休む。巣から出ている時間の約75%は餌を食べるために使い、最後の活動は日の出前20 - 25分ごろに終えることが多い。本種は主に夜行性だが、春 - 夏にかけての繁殖期・および厳冬期には夜間だけでなく日中にも活動する。
Wikipediaウィキペディアより引用
エモンガ、というポケモンのキャラクターにもなりました。
エゾモモンガへの想い
見たことが無い物(世界)を見てみたい。と言う好奇心が私の全ての原動力かもしれません。特に身近なものであればあるほど、手に届く範囲であれば尚更です。
この地元周辺にもまだまだ私が見たことが無い物が沢山存在しています。今回のエゾモモンガもその一つです。
存在を知ったのはほんの数年前。特に希少種でもないので、いつかは遭遇するチャンスもあるのだろうと深く考えもしなかったのですが、最近の人気もさることながら夜行性と言う事もあり、撮影する事そのものが困難を極める事がわかってきました。
であるならば、是非にもその存在を確かめてみようと思い立ったのです。
様々な事前準備
情報収集
まずは情報収集。
今はネットがありますので、ある程度の情報は容易に調べる事ができて便利ですね。
近場でピンポイントに観察できる場所を探しましたが見つかりませんでした。
広く知人にも情報を求めましたが、殆ど空振りに終わり、唯一得られた情報が、
『うちの庭にたまに出てくるよ』
でした。
え?
ってな状況。まずは貴重な目撃情報が得られました。
やはり、結構近くにも生息している模様です。
物的準備
撮影するのですから最低限カメラは必要でしょう。それも望遠で。
観察するだけであれば必要はないのでしょうが、運よくチャンスが巡ってきたらその姿は是非にも記録に残しておきたいものです。
私が選んだカメラはこちら↓

この機種ではデメリットもたくさんありますが、移動に支障のないサイズ・重さである事、超望遠である事、金額的に手が出せる範囲である事、を優先して考慮しております。
もちろん一眼レフがあれば、その方がより鮮明に綺麗な写真や動画が撮れると思います。その分レンズも大きくなってしまいますが、千載一遇のチャンスを物にするには、より高性能なカメラをおすすめ致します。
あとは三脚もあれば便利ですね。
とりあえず撮影するだけであればこれで十分です。
冬の移動手段としてはスノーシューは必須となります。たまに出かけるくらいなら安価なもので十分でしょう。

ポイントの選定
ポイント選び。これが一番大事と言えるのではないでしょうか。
思っていたよりは生息数はかなり多いのだと思います。なので、近場のまとまった林や森にも見つける事が出来るのかもしれませんが、問題はこちら(撮影者)にとって都合の良い場所であるかどうか、と言う事が重要だと思います。
防風林などの木々は密集しており背が高く、発見するのも困難、撮影も困難だと想像できます。
エゾモモンガの大好物の常緑針葉樹であるトドマツやエゾマツは冬でも葉が落ちませんので、格好の隠れ家となります。なので、発見することも困難、撮影も困難であると想像できます。
そして、密集した松の林はとても歩きづらいです。
深い谷や山、車からの移動距離も考慮しなければいけないでしょう。
狙い目としては樹齢が高く背の低い広葉樹林帯が良いのではないかと思います。
そのような場所は存在するのでしょうか?
幸い私の住んでいる中標津町周辺は根釧台地という広大な平野地となっておりますので、エゾモモンガの生息する環境としては申し分ないかと思います。

北海道遺産 格子状防風林(西別岳より)
Googleマップより
また北海道遺産にも選定されている格子状防風林が網の目のように張り巡らせてありますので、様々な野生動物が住み家としている事でしょう。ここにもいるでしょうね、間違いなく。
さて、私が目を付けた樹齢が高く背の低い広葉樹林帯がそこにあるでしょうか?
まずは広大なエリアをgoogleマップで見てみましょう。そして張り巡らせてある格子状防風林を対象からバッサリと外します。広く点在している牧草地と市街地エリア付近も除外します。
さぁ、何が残ったでしょうか?
そう、河畔林です。
山岳地の河畔にはやはり背の高い木々が乱立しておりますが、平地、特に湿地帯の近くには背の低い広葉樹林が広がっています。
エゾモモンガの餌や住み家ともなるハルニレ、ハンノキ、ミズナラなんかもたくさん群生しております。
葉が落ちてしまっている木々であれば個体の発見は容易いのではないでしょうか。
しかも、私が普段釣り歩いているエリアばかりなので、地形はだいたい把握しています。
何の事は無かったのです。通いなれたエリアを再捜索するだけです。

エゾモモンガの調査、痕跡探し

ポイントの選定をある程度済ませておけば、あとは実際に自分の足で歩いて探すことになります。
まず越えなければいけない最初の大きなハードルとなることは間違いありません。
捜索対象となるのは生活の跡となる食痕や糞尿、巣穴です。






休日三日間、3週にわたって見つけ出した痕跡は3か所。
初日から発見できた背景からすると、エゾモモンガの個体数はやはり案外少なくはないのかもしれません。
捜索エリアも人間的に有利である場所に絞り込んでの結果なので、生態の特性でもある臆病であると言う事が生存競争を生き抜く最大の術なのでしょう。
撮影初挑戦!は失敗・・・それは何故か?
エゾモモンガの生態にもありますように、撮影のチャンスは日の出前と日没後、運が良ければ昼間にも、と言ったところ。
まずは日の出前に挑戦。ポイントは最初に見つけた最短距離の場所。


真っ暗闇の中でスノーシューを履き、頭に付けたライト一つで林の中へ入っていきます。
日の出までは約1時間ありますが、空はすぐに明るくなりますので、30分前にはポイントに着いていました。
が、
あたりはまだ暗く目を凝らしてみても確認は出来ず、次第に明るくなり、太陽が出てきても姿を捉える事は出来ませんでした。
3時間超の我慢比べ。惨敗。
二度目の挑戦は日没後を狙い、少し奥の二つ目に発見したポイントです。
同じように日没前にカメラを構え、待つこと2時間超。真っ暗になるまで待ちましたが、出てくる事は無く、寒さと空腹に負け撤退。
さて、何が原因で撮影までには至らなかったのか、検証してみたいと思います。
原因1 音
実際に行けばわかると思いますが、夜の森の静けさは想像以上です。スノーシューで踏みしめる雪の音が辺り一面に響き渡ります。踏みしめる振動も相当伝わっている事でしょう。
防寒着の擦れる音もあなどれません。歩くたびにどうしても腕や脚元がすれるので、これも警戒させるには十分です。
目的のポイントにたどり着く前には、巣穴に閉じこもってしまうのではないでしょうか。
原因2 姿
夜行性の動物なので、やはりこちらの姿は丸見えなのでしょう。音も相まって相当に警戒を与えてしまうのかもしれません。
原因3 精神力・忍耐
移動中は気にはなりませんが、ただじっと待つだけでは体が相当冷え込みます。動けば音がするので、本当にただじっと待つ、その忍耐力も必要。
冷えや空腹、喉の渇き、排泄など人が生きるために必要な動作を極力抑えなければなりません。冬の夜の森でひたすら我慢する精神力・忍耐力も必要となります。
原因を解消して撮影再挑戦!
原因の一つ一つを解消できる方法が見つかりました。
野営です。

利点としては、寒風から身を守り、姿を消し、空腹やのどの渇きを潤し、比較的長時間待ち続ける事が可能になると言う事です。

今回使用したバンドックのテントはこちら↓
風だけ凌げれば良いので、安価なもので良いと思います。私には必要十分でした。
冬場ですので地面にペグが刺さらない場合を想定して自立式のテントの方が、私は良いように思います。

少々の雪を除けるために分割式のスコップがあると便利かもしれません。

一酸化炭素の警報器もあったほうが良いでしょう。
案の定、少しの暖をとる為にコンロに火をつけると直ぐに警報機が鳴り始めます。
警戒を解くためにも、自分が死なない為にも音がならないように注意が必要です。
さぁ、いよいよ本気モードで撮影に挑戦してみたいと思います。
さすがに3度目ともなると撮るまで帰ってこないという意気込みではあります。
食料や水、テント、スコップ等の荷物が増えたので、今回はソリを用意して重い荷物はソリに括りつけました。ザック1、ソリ1の重装備です。
暗闇の移動の行程が面白そうなので、録画してみました。↓
ただただ暗闇を歩いている動画なのですが、私的にはこちらの動画の方が好みです。変人ですね。
結果としては、夜明け前1チャンス、昼間1チャンスがあり、はじめて撮影の機会をもらう事が出来ました。
そうとうミスショットもありましたが、きちんと全身を捉える事ができており、初回としては大変満足しております。

冒頭の引用にもあります通り、『厳冬期には夜間だけでなく日中にも活動する』という期間に該当したのかもしれません。現に気温はマイナスの15℃を下回っていました。
日中もマイナス7℃付近が最高気温だったと思います。






エゾモモンガの撮影を終えて
正直、ここまでの装備や準備は必要ないと思います。
近場のポイント探索や、よく生態を観察することで写真撮影はますます容易になる事でしょう。
今回の撮影は私自身が初挑戦と言う事もあり、かなり無理をした結果です。
なので、成果としては何とか挙げる事が出来ました。
何にしてもこのエゾモモンガだけにターゲットを絞ると空振りした時の精神的ダメージは計り知れません。
現に私がそうでした。
他の目的も併せてついでに探索、観察、撮影とした方が気分的にも楽かと思います。
例えば、釣りをしながら辺りを探索してみたり。
他の野鳥観察や、スノーシューでのトレッキングメインで森に入ってみたりと様々な目的を兼ねて行う事をおすすめ致します。
それでダメであったのなら今回はご縁が無かったと言う事で潔くあきらめましょう。
決して無理はしない事です。


ヒグマの爪痕
あと、雪解けのシーズンに入りましたら、ヒグマの活動時期とも重なります。容易に野営が出来る環境ではなくなるため相当な注意が必要となります。厳冬期にも暖かい日が続くことで、一時的に活動することもあるらしいので、ヒグマ対策と状況判断は適切に行わなければなりません。
最後に
私が撮影した画像と映像は何処にでもあるような代物ではありますが、その裏では結構な努力がありますよ、と言うお話で・・・
見たことが無い物をまた一つ見る事が出来ました。
何かの参考になりましたら幸いです。
では、また。
追記
地元中標津町にもエゾモモンガの痕跡発見!




まだ本体の確認はできていませんが、自宅近くの河畔林にエゾモモンガの痕跡を見つける事が出来ました。
今後も調査を継続していきます。
さらに追記
ついに中標津町にてエゾモモンガの撮影に成功いたしました!
ランキングにご協力ください。m(_ _)m↓
ツイッターもやってます!
北の釣友byへたくそ釣り師
Follow @northfishers
YouTube動画もあります!
チャンネル登録お願いします↓
登録1000人↑チャレンジ中!